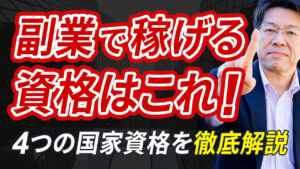今回は「中小企業診断士の一次試験で7科目をどう戦うか?」について、私の実体験をもとに、戦略的な勉強法を紹介します。
一次試験は科目数が多く、やみくもに全科目を同じ熱量で勉強してしまうと、時間が足りなくなったりモチベーションが下がってしまいます。そこで私は、効率よく合格するために科目ごとの重み付けやスケジュール管理を徹底しました。
1. 二次試験に必要な科目を優先する
中小企業診断士試験では、一次試験はあくまで通過点です。最終目標は二次試験の合格。そのため、一次試験の勉強も二次試験で必要となる科目を重視するのが鉄則です。
私が重視したのは次の3科目です:
- 企業経営理論
- 財務・会計
- 運営管理(生産管理)
この3つは二次試験でも活用するため、深く理解することが後々の合格に直結します。逆に、次の科目は二次試験では使わないため、足切りを避けるレベルでOKです。
- 経済学・経済政策
- 経営法務
- 中小企業政策
また、経営情報システムは一部で二次試験に影響することもあるので、余裕があれば対策する程度の位置づけにしていました。
2. 点数が安定しやすい科目を優先する
7科目の中には、年度によって点数が安定しやすい科目とブレやすい科目があります。私は過去問5年分を解いてみて、点数の安定性を以下のように感じました。
安定しやすい科目
- 経済学・経済政策
- 運営管理
これらは出題傾向が安定しており、努力が得点に反映されやすいと感じました。
ブレやすい科目
- 経営情報システム
- 経営法務
トレンドや制度改正の影響を受けることが多く、点数がブレやすいです。私はIT出身ですが、それでも情報システムで50点の時もあれば80点の時もありました。
こうした特性を見極めて、安定得点できる科目を先に仕上げる戦略が合格には有効だと思います。
3. ゴールデンウィークまでに全科目を一通り終わらせる
私は4月末までに7科目すべてを一通り学び終え、その後は過去問演習中心に切り替えました。
具体的には、過去5年分を3〜4周、計20回くらい回すイメージです。土日は本番形式で全科目を解き、平日は苦手科目に集中するというリズムで勉強しました。
こうすることで、知識の定着が進み、試験本番までに自然と仕上がっていく感覚がありました。
4. 二次試験の勉強も少しだけ先取りする
一次試験に全力を注いだ私は、二次試験の対策が9月スタートとなり、正直ギリギリでの合格でした。今振り返ると、「6月頃に少しでも二次試験の勉強をしておけばよかった」と感じています。
特に財務・会計は、二次の問題を通じて理解が深まります。一問一答ではなく、実際に計算しながら考える問題形式が、一次の知識の「点」を「線」に変えてくれました。
余裕があれば、企業経営理論や運営管理も二次目線でさらっておくと、一次試験の勉強にも良い影響が出てくると思います。
5. 暗記科目は前日の仕込みが重要
一次試験は2日間に分かれています。2日目は暗記科目(経営法務・情報システム・中小企業政策)が集中するため、私は前日に「自分用暗記メモ」を見返すことで最後の追い込みをしました。
A4用紙1〜2枚に「どうしても覚えられなかった部分」だけをまとめておけば、試験前日の短時間で効率よく復習できます。
私はこれを実践したおかげで、暗記科目で足切りを避けることができました。
まとめ|中小企業診断士 一次試験は“戦略”がすべて
中小企業診断士の一次試験は、「満点を取る試験」ではなく、「420点を取って通過する試験」です。
だからこそ、戦略的に勉強することが何より重要です。不得意科目は最低限にとどめ、得意・得点しやすい科目に時間を投下する。これだけで合格の可能性はグッと高まります。
これから中小企業診断士を目指す方の参考になれば幸いです。