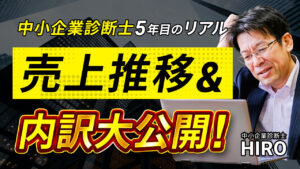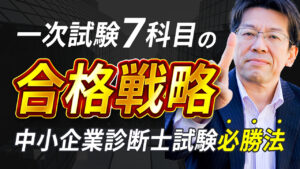今回は「中小企業診断士 経営法務」の一次試験対策について解説します。
この科目、苦手な人が本当に多いんですよね。かく言う私も、診断士試験をストレート合格したとき、唯一60点を超えられなかったのが経営法務でした。
その後、行政書士としても法律を扱う仕事をしてきましたが…
久々に最新の過去問を解いてみたところ、36点という結果に。
つまり、「実務で使える法律の知識」と「試験で点を取る知識」は別物。
合格するためには、試験対策として割り切った勉強法が必要なのです。
この記事では、「中小企業診断士 経営法務」で足切りを回避し、効率よく合格ラインに到達するための5つの戦略をお伝えします。
経営法務は“点が取りづらい”科目
経営法務は、中小企業診断士の一次試験7科目の中でも特に「得点しにくい科目」と言われています。理由は以下の通りです。
- 法律独特の言い回しで文章が読みにくい
- 単純な暗記では解けない問題が多い
- 出題形式がひねっている(会話形式など)
- 他科目と比べて得点効率が悪い
にもかかわらず、全体の総得点420点を超えるためには無視できない存在。
だからこそ「経営法務対策」は、いかに効率よく合格ラインまで持っていくかが鍵になります。
中小企業診断士 経営法務 対策の5つの戦略
1. 足切りを防ぐことを最優先に
まず、経営法務でやるべきは「60点を目指す」ことではなく、確実に足切り(40点未満)を回避することです。
現実的な目標スコアは48点〜52点。
合格に必要な420点のうち、経営法務では“最低限の点数”だけを取り、他の得意科目で稼ぐ戦略が有効です。
2. 「会社法」と「知的財産権」に集中する
出題傾向を分析すると、この2分野が全体の7割以上を占めています。
- 会社法:設立、機関、再編など(毎年9問前後)
- 知的財産権:特許権・意匠権・商標権の違いなど(毎年9問前後)
この2つの分野でしっかり得点できれば、他の分野を“鉛筆転がし”で乗り切っても合格点に届く計算です。
基本に忠実な出題が多いため、深く掘りすぎず、頻出項目を繰り返し復習するのが効果的です。
3. 民法・英文契約などは“捨てる選択肢”も大事
経営法務の中には、「出題数が少ない・理解に時間がかかる」分野もあります。
特に以下のような分野は、割り切って捨てるか、最低限に抑えるのがおすすめです。
- 英文契約:英語が苦手なら初手で捨てる
- 民法:出題頻度は低め。契約・相続などの品質問題だけ対応
- 労働法など:出題頻度が低く、対策コスパが悪い
「全部やろう」と思わず、自分にとって理解しやすい分野・点が取りやすい分野に集中することが大切です。
4. 過去問は“選択肢ごと”に理解する
経営法務では、正解を当てるだけでなく、なぜ他の選択肢が間違っているのかを考えることが重要です。
たとえば、会社法の問題で「い」が正解だとしても、
「あ・う・え」の選択肢の誤りポイントを調べることで、一気に周辺知識が身につきます。
1問から4つの論点を学ぶイメージで、時間効率も知識定着も大幅アップします。
5. ノートより“暗記メモ”で試験直前対策
苦手科目ほどノートをまとめたくなりますが、診断士試験の一次知識は試験までの使い捨てです。
私が実践していたのは「暗記できなかった項目だけメモする」方式。
- 覚えにくいポイントだけ紙に書く
- 過去問を解くたびに、できなかった内容だけ追加
- 最終的にA4用紙1〜2枚にまとめて、試験前日に見る
このやり方なら、復習もしやすく、試験当日に効率よく見直せる資料が完成します。
実務では重要でも、試験では“割り切り”が大事
経営法務は、診断士として独立後も重要な知識にはなります。
契約書や法人設立、補助金関連など、法律の知識は実務で多く使います。
ですが、試験では別物。
実務経験や行政書士資格を持っていても、試験問題のクセや出題傾向に慣れていないと高得点は難しいというのが現実です。
まとめ|中小企業診断士の経営法務は「戦略科目」
最後に、経営法務を攻略するためのポイントをまとめます。
- 満点を目指さず、足切りを避けることが最優先
- 会社法・知的財産権に集中投資
- 民法や英文契約は捨てる勇気も必要
- 過去問は正解だけでなく選択肢全体を分析する
- ノートではなく、暗記メモで復習効率を上げる
中小企業診断士の一次試験を乗り越えるためには、「どの科目に力を入れるか」だけでなく、
「どこに力を入れすぎないか」も合否を分ける重要な戦略です。