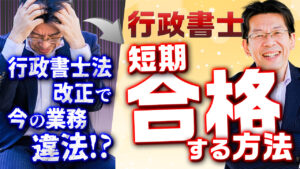今回は、YouTubeでもご質問いただいた「3士業(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士)の違い」について、営業方法や稼ぎ方、適性の違いなどをリアルな経験をもとに解説していきます。
夫婦で士業をしている立場からも、それぞれの資格の特徴がよく見えてきたので、これから資格を取って開業しようと考えている方には、ぜひ参考にしていただきたい内容です。
1. なぜこの3士業に注目するのか?
この3士業に共通するのは、「働きながらでも目指せて、独立も視野に入れられる国家資格」であることです。
司法書士や税理士のような高難易度資格は勉強時間も多く、年齢やライフスタイルによっては現実的に取りにくい。
一方でFPや簿記は取得しやすいですが、独立して稼ぐのは難しい面も。
中小企業診断士、社労士、行政書士は、「実務に活かしやすく、独立・副業も視野に入れやすい」現実的な資格としておすすめできます。
2. 稼ぎ方の違い
■中小企業診断士:バリエーション豊富な収益モデル
- 公的案件(商工会議所、よろず支援拠点など)
- 補助金申請支援
- 経営コンサルティング
- 顧問契約
→ 経営全般に関わるため、どんな社会人経験も活かしやすい資格です。
■社会保険労務士:顧問契約で安定収入を得やすい
- 労務管理・社会保険手続き
- 就業規則整備
- ハラスメント相談対応など
→ 基本は月額顧問契約スタイルで、積み上げ型のビジネスモデルです。
■行政書士:単発中心、仕組み化で勝負
- 許認可(建設業、風営法、古物商など)
- 相続、外国人就労、遺言関係など
→ 単発型なので「どうやって継続受注を生み出すか?」が鍵。
3. 企業内での活かし方の違い
- 社労士:人事労務部門で活かしやすく、企業内資格者として活躍する人も多い
- 診断士:金融・経営企画部門などで“評価アップ”として使われることが多い
- 行政書士:基本的に企業内で活用はできず、開業前提。副業との相性も悪め
4. 営業の違いとそのコツ
■中小企業診断士
- 協会や商工会議所経由で仕事獲得
- 支援先で信頼を得て紹介へ
- 補助金案件はコンサル会社や他士業からの依頼も多い
■社会保険労務士
- 勉強会・異業種交流会などで地道にネットワーク拡大
- 信頼を積み重ねて顧問契約へ
■行政書士
- 特定業界に特化して“専門家”としてポジション確立
- ニッチ分野(例:外国人雇用、ドローン、M&A)で先行者利益を狙う
- 情報発信・セミナー開催が営業手段に
5. 自分に合った資格の選び方(適性とネットワーク)
| 資格 | 適性 | 活かせる経験 | 主なターゲット |
|---|---|---|---|
| 診断士 | 幅広く応用が利く | すべての業種・職種 | 社長・企業 |
| 社労士 | 人事・労務に関心ある人向け | 総務・人事経験など | 社長・企業 |
| 行政書士 | 実務経験不要で始めやすい | 経験不問 | 個人・小規模事業者 |
→ 自分の人脈・ネットワークにどのターゲットが多いかも重要な判断基準です。
6. スケーラビリティとビジネスの拡大性
- 診断士:属人的でスケールしにくいが、爆発的に稼ぐことは可能
- 社労士・行政書士:定型業務が多く、事務員を雇って拡大しやすい
ヒロ家の場合も、所得は同じくらいでも、売上は社労士(妻)のほうが大きいです。事務員を雇っていることが一因です。
7. まとめ:どの資格があなたに向いているか?
結論として、どの資格が良いかは一概には言えません。大事なのは、あなたの適性・経験・ネットワーク・ライフスタイルに合った資格を選ぶことです。
今回の内容が、資格選びや開業準備の参考になれば幸いです。