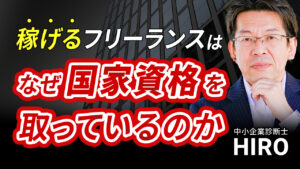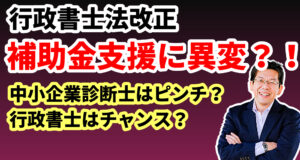ダブルライセンスは本当に意味がある?資格を増やしても仕事に繋がらない7つの理由を、中小企業診断士・行政書士の私が経験をもとに解説。士業で開業した人が陥りやすい落とし穴とは?
こんにちは。中小企業診断士・行政書士のHIROです。
今回は「仕事がないから資格を増やすのは意味がない」というテーマで、士業で開業した人がついやってしまいがちな誤解についてお話ししたいと思います。
ダブルライセンスやトリプルライセンスを目指す人は多いですが、それが本当に“仕事につながる選択”かどうか、一度立ち止まって考えてみませんか?
仕事がないから資格を増やすのは意味がない7つの理由
第7位:資格を持っているだけでは仕事は来ない
「資格を取れば自然と仕事が舞い込む」と思っている人は意外と多いですが、資格=営業力ではありません。
資格があるだけで仕事が来るなら、そもそも“今ある資格”で仕事が来ているはず。
大事なのは、どう発信し、どうアプローチするかです。
第6位:資格取得が目的化し、行動が止まる
資格に合格すると達成感がありますよね。
でもその快感を求めて「次は何を取ろうか?」と勉強に逃げるようになると、本末転倒です。
仕事がないなら勉強よりも、営業や発信に時間を使うべきです。
第5位:営業力がなければ資格を並べても選ばれない
名刺に資格をたくさん書いても、依頼されるのはたった一人。
資格数よりも「あなたに頼みたい」と思ってもらえる魅せ方が重要です。
その時間をSNS発信やブログ・YouTubeに使った方が、はるかに効果的かもしれません。
第4位:専門性がぼやける
あれもこれもできると、結局「この人は何の専門家?」と思われてしまう。
たとえば寿司だけ握れる職人と、何でも作れる料理人がいたら、寿司を食べたい人はどっちを選ぶでしょうか?
士業も同じ。資格を増やすより、特化することで信頼は深まります。
第3位:他士業から紹介されにくくなる
士業はお互いに仕事を紹介し合う文化がありますが、資格を持ちすぎると「自分の仕事を取られるかも」と警戒されることがあります。
税理士×診断士、社労士×行政書士など、“かぶりすぎる”と紹介ルートを断たれることも。
第2位:維持費がかかる
資格によっては登録費・年会費・協会費などがかかります。
例えば行政書士は毎月7,000円以上、社労士も同程度。3つも4つも資格を持つと、会費を払うために働くような状態になってしまうことも。
第1位:体はひとつしかない
資格を増やしても、自分の時間は増えません。
士業の多くは属人性が高く、仕事の分業や外注がしにくいため、複数の資格分の仕事を自分一人でこなすのは限界があります。
結果、パンクしてしまい、クオリティや信頼を落とす可能性もあります。
ただし、資格を増やすのが効果的なケースもある
すべての資格取得が無意味というわけではありません。
「1人の顧客から受けられる仕事を増やす」という目的であれば、資格の追加は非常に有効です。
たとえば私の場合、創業支援の相談をよく受けていたことから、法人設立手続きも任せられるようにと行政書士を取得しました。
その結果、相談→設立→補助金という一連の流れをパッケージで提供できるようになり、単価アップにもつながりました。
資格の“組み合わせ活用”が有効なパターン
- 行政書士 × 社労士: 許認可+労務管理で創業者の継続支援
- 中小企業診断士 × デザイナー: 補助金+販促物制作で一気通貫支援
- ライター × FP: 資産運用メディアの監修・執筆案件に対応
ポイントは、「新しい顧客を取る」より「既存顧客からの単価を上げる」という視点での資格取得です。
やるべきは“資格の追加”より“発信と営業力の強化”
もし「資格はあるけど仕事がない」のであれば、やるべきことは次の資格の勉強ではなく、営業と発信の改善です。
・ホームページは検索されているか?
・SNSで専門性を伝えられているか?
・YouTubeやブログで「あなたの人柄」が伝わっているか?
仕事が来ない理由は「知られていない」ことに尽きる場合も多いです。
まとめ:「仕事がない→資格を増やす」は危険な思考ループ
資格は信頼の証ではありますが、「資格を取れば仕事が来る」と思っている限り、結果は変わりません。
大切なのは、今持っている資格をどう活かし、どう発信していくかです。
「仕事がないから資格を取る」のではなく、「今の仕事をより深く・広くするために資格を取る」という考え方であれば、意味のある投資になります。